- おおつまなかのちゅうがっこう・こうとうがっこう
-
大妻中野中学校・高等学校
- Otsuma Nakano Junior & Senior High School
- 種別中等教育学校または中高一貫校等 地区関東地区
- 主な活動分野生物多様性, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, ジェンダー平等, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困, グローバル・シチズンシップ教育(GCED)
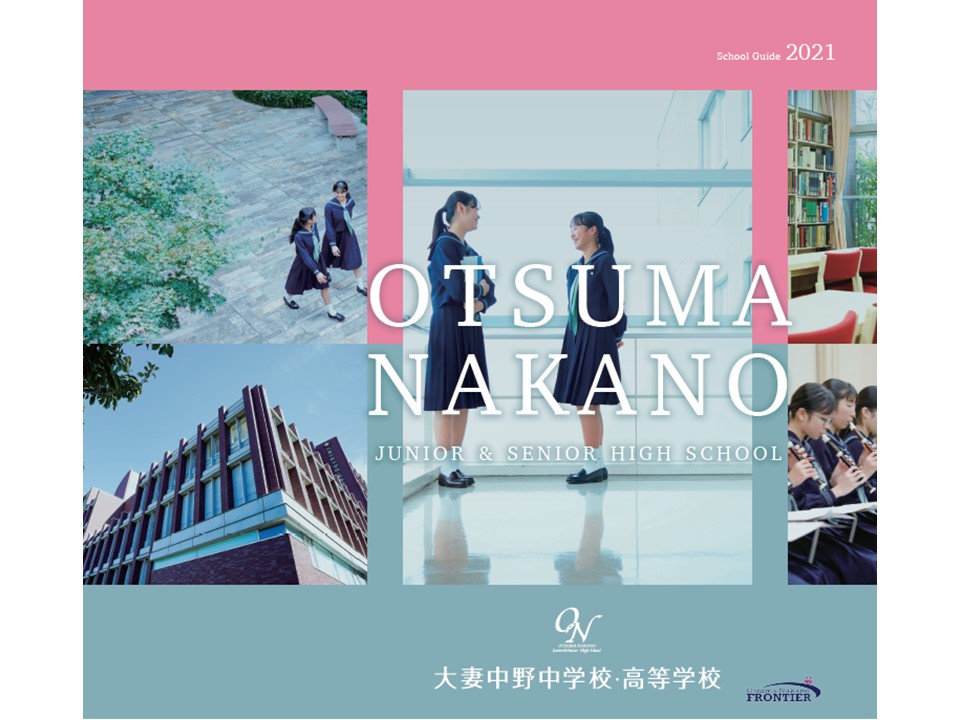
| 所在地 | 〒164-0002 東京都中野区上高田2丁目3番7号 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3389-7211 |
| ホームページ | https://www.otsumanakano.ac.jp/ |
| 加盟年 | 2022 |
2024年度活動報告
生物多様性, 海洋, 減災・防災, 気候変動, エネルギー, 環境, 文化多様性, 世界遺産・無形文化遺産・地域の文化財等, 国際理解, 平和, 人権, ジェンダー平等, 福祉, 持続可能な生産と消費, 健康, 食育, 貧困
本校は、「学芸を修めて人類のために」を建学の精神とし、「地球市民として、Society5.0における持続的なより良い社会の創造と自らの幸せを紡ぐことのできる人材の育成を目指す」というスクールミッションを掲げている。 このミッションは、 ユネスコスクールが重点的に取り組む教育の3つ柱*と重なっており、このスクールミッションを具体的なカリキュラム、各種のプログラム、学校行事で取り組みに落とし込み、取り組んでいる。
※【ユネスコスクールが重点的に取り組む3つの柱】
①地球市民および平和と非暴力の文化
②持続可能な開発および持続可能なライフスタイル
③異文化学習および文化の多様性と文化遺産の尊重
特に2024年度は、これまでの本校のユネスコスクールとしての活動実績と今後の更なる取り組みを土台に、文部科学省事業である WWL(ワールドワイドラーニング)コンソーシアム構築事業拠点校へ申請し、その計画が採択された。 本校のWWL拠点校としての構想名は、「繋ぐ・行動する – “Beyond School” アプローチによる協働型の地球市民教育“であり、この構想はそのまま本校のユネスコスクールとして取り組みになっている。
全校生徒対象の地球市民教育としては、中1「自己探究」、中2「環境探究」、中3「歴史・平和探究」を、探究学習と宿泊研修などで実施している。 高校では、自ら課題を発見し、リサーチし、発表する「総合的な探究の時間」を中心に取り組み、各種発表会、コンテスト、模擬国連会議など、学校を超えたプログラム(Beyond School アプローチ)にチャレンジしている。
また、本校では、プロジェクト型学習と複言語教育(英語、フランス語)、サービスラーニングなどを核とした独自のリベラルアーツカリキュラムを展開するグローバルリーダーズコース(GLC)を設置しており、独自の学校設定教科GIS(グローバルイシュースタディ)などで、世界の課題を英語で学ぶクロスカリキュラムを実施し、文部科学省・筑波大学主催の全国高校生フォーラムを主とした目標として取り組んでいる。 さらに学年横断型の生徒主導プロジェクト課外学習として、「フロンティアプロジェクトチーム」、「S-TEAM(IT活用探究学習プロジェクト)」などのプログラムに取り組み、先進的な地球市民教育のカリキュラムモデル開発を行っている。
大妻中野のユネスコスクールの活動、探究的な取り組み、地球市民教育の成果発表の場として毎年、9月に文化祭「Global Arts Festival」と、2月に「グローバル教育発表会 」を開催し、広く有識者、ユネスコスクール関係の方に公開している。 さらに、2024年度は、特に以下の学校を超えたBeyond School アプローチでの協働において、「本校の取り組みで修得した学芸を、地域や地球規模の具体的な課題にあてはめ、創造的に考え行動する地球市民的視野を持ったリーダーの育成」を目標に様々な実践に取り組んだ。以下、主な取り組み事例である。
① 第5回ユネスコスクール関東ブロック大会 (2024年10月5日、玉川大学)での取り組み
この玉川大学で開催された第5回ユネスコスクール関東ブロック大会では、主催の玉川大学ユネスコクラブの学生、大学の先生方、及び同じくユネスコスクールである東京都立山崎高等学校と協働し、 本校のフロンティアプロジェクトチームの生徒達を中心に、「国際対立の解決に向けたユネスコスクール・ユースの探究ワークショップ」 というテーマで世界平和の喫緊の課題に取り組んだ。 事前の学習の段階から、「異文化学習」と「葛藤解決」に焦点を当てながら、取り組みを進め、充実したプロセスとともに、大会当日の発表と議論は、優れたユネスコスクールとしての取り組みとなった。
また、 この大会では、本校の「地球市民教育」及び「異文化学習、文化の多様性への学び」の実践としてのフランス語授業チームの生徒達が、その成果をポスターセッションで発表した。
https://sites.google.com/view/unescoschool-kanto5th/
② 学校間交流プログラム – 相互訪問による異文化学習、文化の多様性への学び の実践 –
WWL連携校 – 台湾 聖功女子高級中學 Sheng Kung Girls High School / マレーシア Sri Aman Girls High School
2024年5月に、高校2年次の教育旅行プログラムであるグローバルスタディツアーの台湾コースおよびマレーシアコースでは、直接、現地の学校を本校生徒が訪問し、教育交流を行い、相互の文化を学び合うプログラムを実施した。 それぞれの学校の優れた教育実践とともに、その文化を生徒同士が発表したり、ワークショップを行うなどで、主体的、協働的に学びあうことができた。
また、台湾の聖功女子高級中學Sheng Kung GHSについては、この学校の生徒30名と先生方が本校を訪問。 本校の生徒が主体となり、受け入れ交流プログラムを企画、実施し、日本の学校文化を直接、体験するプログラムを実施した。 これにより、相互の訪問が実現に、さらに深いレベルでの交流が進んだ。
③ 高大連携によるグローバル課題への深い学びの実践 – ユネスコスクールの3つの柱をテーマに
・ 順天堂大学(本校高大連携大学)による「国際協力、国際保健医療」に関するグローバル課題の学び
順天堂大学 国際教養学部・大学院医学研究科・国際教養学研究科の白山芳久先生による高大連携プログラム。 ヴァーチャルにラオスを旅して、病院や村を訪ねる体験し、Health Literacy というキーワードから、グローバルな視点で、Well-Being を学んだ。
・ 東京農業大学教授、松林先生と 「生物の豊かさを守る!」連携授業での学び
持続可能な環境教育と生物多様性と野生動物の保護という観点から、深い学びを体験しました。 SDGs No.15 「陸の豊かさを守ろう 」 に直接、繋がる松林教授によるボルネオ島での動物保護、研究の成果について学んだ。 また、この取り組みは、5月の国際デー 「生物多様性の日」の周知のため取り組みでもあった。
・ 上智大学国際教養学部FLAでの日本における難民問題に関する深い学び
上智大学国際教養学部のDr. David Slater 教授による「日本における難民問題」に関する大妻中野生のための特別授業を実施。 上智大学国際教養学部に進学した本校卒業生に中心になり、企画、実施された地球市民としての意識を高めるプログラムで、6月20日の国際デー「世界難民の日 」の周知のための取り組みでもあった。
・ テンプル大学ジャパン(本校連携大学)との連携による高1GISの特別授業での学び
本校の高校1年の授業グローバルイシュースタディズのカリキュラムとして、テンプル大学ジャパンキャンパス教授の堀口 佐知子先生 Dr. Sachiko Horiguchiの特別授業を2回にわたって実施。 テーマは、 “Understanding the Impacts of War on Women’s Roles & Ideas of Femininity“ ジェンダー公平に関する社会課題に英語で取り組んだ。
④ ユネスコスクールとの連携による「平和」学習 ノーベル平和賞と被団協および平和について学ぶ
2024年は、被爆者団体である「被団協(日本原水爆被害者団体協議会)」がノーベル平和賞を受賞したことを踏まえ、ユネスコスクールからの呼びかけに対応して、中3(公民)、高1(公共)の授業のカリキュラムとして、被団協のリサーチと ノーベル平和賞が果たす役割と、平和のために自分たちができることについて考え、発表した。
⑤ 「国連デー」へ周知活動 – ユネスコスクールとして皆で「国連」の意義を考える
10月24日は、国際連合が設立された日を記念する「国連デー」にちなんで、本校の生徒プロジェクトチームであるフロンティアプロジェクトチームが、学校全体に向けて、国連について知って考えてもらうために、この放送を通じてた周知活動に取り組んだ。
https://www.otsumanakano.ac.jp/archive/62219/
⑥ 第9回UNESCOユースセミナー (2024.10/19 & 20) へのチャレンジ
「心とからだで感じるジェンダー公平 (gender equity)」というテーマで開催された第9回UNESCO ユースセミナー(東海大学国際学部主催)に、本校生徒が、準備委員として、運営側で参加。貢献した。特に本校の中学生には貴重な学びの機会となった。
https://www.u-tokai.ac.jp/news-challenge/1108042/
⑦ ACCU アジア太平洋青少年相互理解推進プログラム へのチャレンジ
本校の生徒が、ユネスコ・アジア文化センター(以下ACCU)主催の「アジア太平洋青少年相互理解推進プログラム”BRIDGE Across Asia Conference 2024″ (以下BAAC)」へ参加した。 アジア5か国 (韓国・日本・タイ・インド・モンゴル) 各国の代表として選出された高校生が英語を共通言語としてディスカッションや模擬国連、プレゼンテーションを行い、その成果を校内で広く共有した。
https://www.otsumanakano.ac.jp/archive/62353/
来年度の活動計画
2025度の活動計画
本校のこれまでの取り組みである探究学習を活用した学年テーマ別探究取り組み(中1「自己探究」、中2「環境探究」、中3「歴史・平和探究」、高校「自由課題探究」)をそれぞれの学年の学校行事と関連させて継続する。
ユネスコスクールの重点課題を意識した探究的な教科学習として教育課程に位置付けている中1 国語探究、 中2 社会探究、 中3 数学探究を継続、発展させる。
中3での教育旅行(沖縄 平和・環境学習旅行)、 高2でのグローバルスタディツアー(マレーシア、台湾、京都・奈良への教育旅行)を通して、地球市民、平和、持続可能な開発、異文化、文化多様性、文化遺産に関する探究を体験から深める。
海外連携校との協働によるグローバル課題についての探究学習をよりいっそう進めていく。 台湾のSheng Kung Girls High School とは海洋問題についてプロジェクトが具体的に進んでおり、他の海外連携校とも一緒に取り組む。
本校グローバルリーダーズコース設定教科「Global Issue Study」による、英語やフランス語を用いた課題探究活動を継続して、実施する。
高大連携を一層進め、大学の専門的な学術リソースを活用し、より深い学び、リサーチを行い、大学生とも連携したディスカッションな発表会に取り組む。
地球市民教育、SDGs探究、異文化学習、文化多様性、文化遺産などに関する探究成果発表の場としての「Global Arts Festival – 文化祭」、「WWL成果発表 Presentation Contest 」を継続して実施する。
カナダ、アメリカ、ニュージーランド、オーストラリア、フランス、ドイツ、アイルランド、イギリス等への短期から1年留学プログラムにより、地球市民教育、異文化学習を促進する。
地球市民リーダーの育成を目標とした学年横断型探究課外授業「フロンティア・プロジェクト・チーム」、STEAM教育を先進的に行う課外授業「S-TEAM」を継続実施する。
玉川大学、成蹊大学、東海大学、大妻女子大学、その他ユネスコスクールと一層連携した取り組みを行う。
第6回ユネスコスクール関東ブロック大会(成蹊大学、玉川大学、東海大学、創価大学などの共催により実施予定)へ積極的に参加し、本校による生徒発表とその成果を校内外への一層の普及に努める。
